これといって新鮮な話題でもなく、まあそうでしょうねえと思ったけど、場つなぎ的に取り上げてみたり。
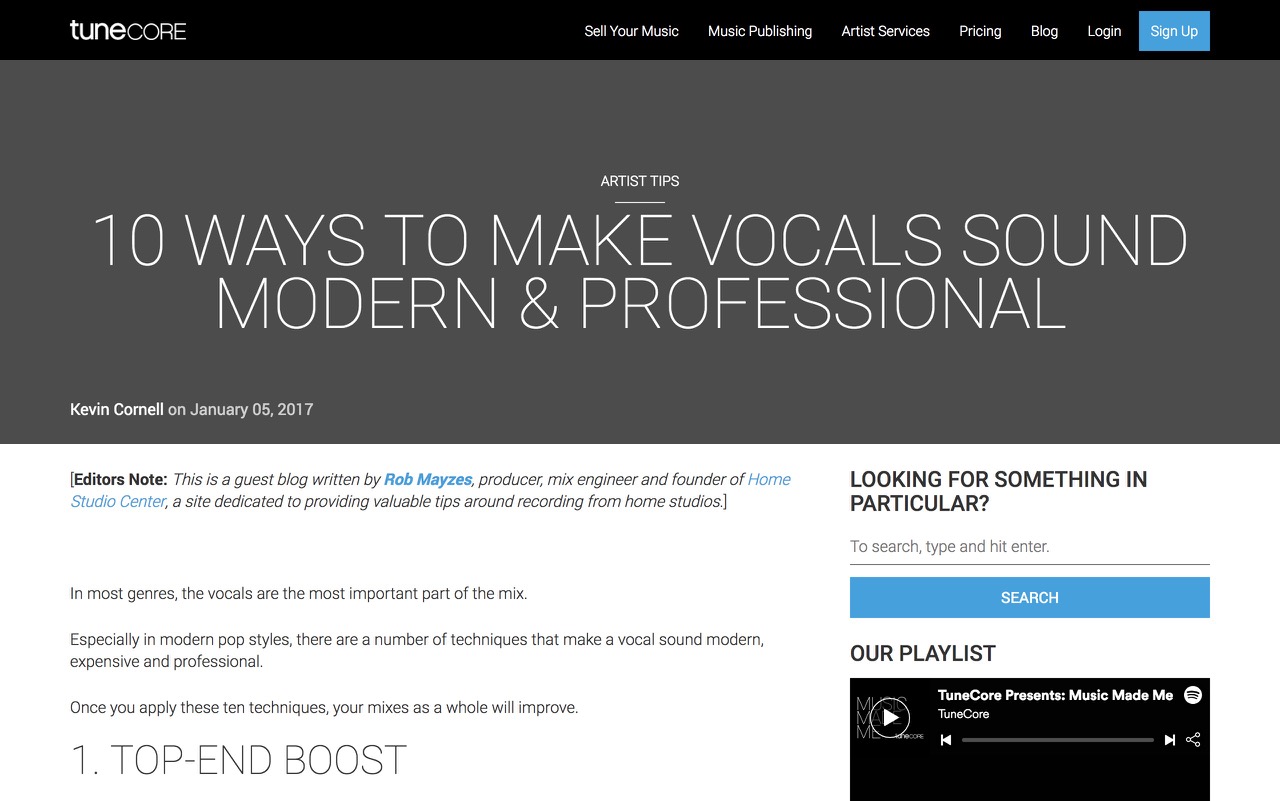
多くのジャンルでボーカルはミックスの中核を担う部分。昨今のポップスでは数多くのテクニックが存在する。
以下10個のテクニックを活用し、ミックスを改善しよう。■目次
トップエンドをブースト
高品質っぽくする手っ取り早い方法。
高級マイクは高い周波数帯域が持ち上がっているのでその真似をするわけだ。
Slick EQなど用いて10kHz辺りを2dBほどブーストしてみよう。ディエッサーを使う
ハイを上げると摩擦音が気になり出す。
そんなときの必需品だ。
プラグインチェインの最上段か最下段に挿すのがベスト。残響を除去
EQでポイントを探して部屋鳴りを除去する。
抑揚をオートメーションで制御
今の時代も抑揚は大事。
これらの調整にはコンプレッサーじゃ不十分なのでオートメーションを活用したい。
コンプレッサー入力前のゲインで調整することを勧めたいが、フェーダーオートメーションでもよい。ピークが飛び出さぬようリミッターを
狙い過ぎるとコンプレッサー過剰な音になってしまうので、2dB程度のリミッターに留めておきたい。
マルチバンドコンプレッション
音域の違いで声質は変わってしまう。
声の色々な状態にEQで対応するには限界があるためマルチバンドコンプレッションを活用する。高域をサチュレーションで
EQで高域を調整するのにも限界はある。
高域を歪ませて倍音を作ることができる。リバーブの代わりにディレイを
リバーブを使うと歌が奥に引っ込んでしまう。
ステレオのスラップバックディレイを使って奥行きとステレオ感を作ろう。
フィードバックは抑えめ、左右に若干の時間差を作る。
50-200msのディレイタイムが程よい感じだ。わずかにプレートリバーブをかける
奥行きとステレオ感がもっとほしいときはプレートリバーブを試してみる。
リバーブ感を感じられるとこまで上げて、それからほんの少し下げるとちょうどいい。
最低限のディケイに縮め60msのプリディレイを上げるとグチャッとした感じにならず空間っぽさも出る。微かなコーラスエフェクト
ボーカルに深みと艶を与えるには微かなコーラスを加えるのがいい。
これまたコーラス感が感じられる程度に上げてほんの少し戻すとちょうどいい。まとめ
ボーカルは他の楽器よりも丁寧にミックスする必要がある。
しかし以上の10個のテクニックで格段に近代的でプロっぽいサウンドになるだろう。
先に紹介した「Automation in Mastering」の記事では「コンプレッサーのあとのフェーダーオートメーションじゃないと意味がない」と書かれていた一方で、こちらの記事はコンプレッサーに入力する前にオートメーションさせることが推奨されています。
僕の場合はコンプレッサーより前が基本で、コンプレッサーによる飽和を防ぐため。
音量だけを操作するならコンプレッサー後でいいのだけど、飽和感を後で取り除くのはほぼ不可能だから、まずコンプレッサーに”ぶっ込み”過ぎないようにします。でももちろん好き嫌いはあり。
エンジニアさん付きの現場なら「ナチュラルに録ってほしい」と伝えるとよいかと。
少しだけ補足。
マイクの特性の影響でボーカルやドラム、ギターの高い帯域を不足気味に感じたなら、擬似的に補完するものとしてフリーウェアのRoth-AIRが意外といいです(Daniel Rothmann “Roth-AIR”(配布終了))。
音声のレベルに合わせて特定の帯域に微量にノイズを加えるもので、EQを使わずに音声を手前に引きずり出せる効果もあります。
少し低めの帯域にセットして母音を聞き取りやすくもできます。
帯域は8kHz上限なので、一辺倒に使うと痛い響きになる点に注意。また環境によってはエフェクトチェーンの最後に挿さないと効かないことも。
あくまで擬似的な処置を加えるものですがダメ元で試してみるとよいかと。